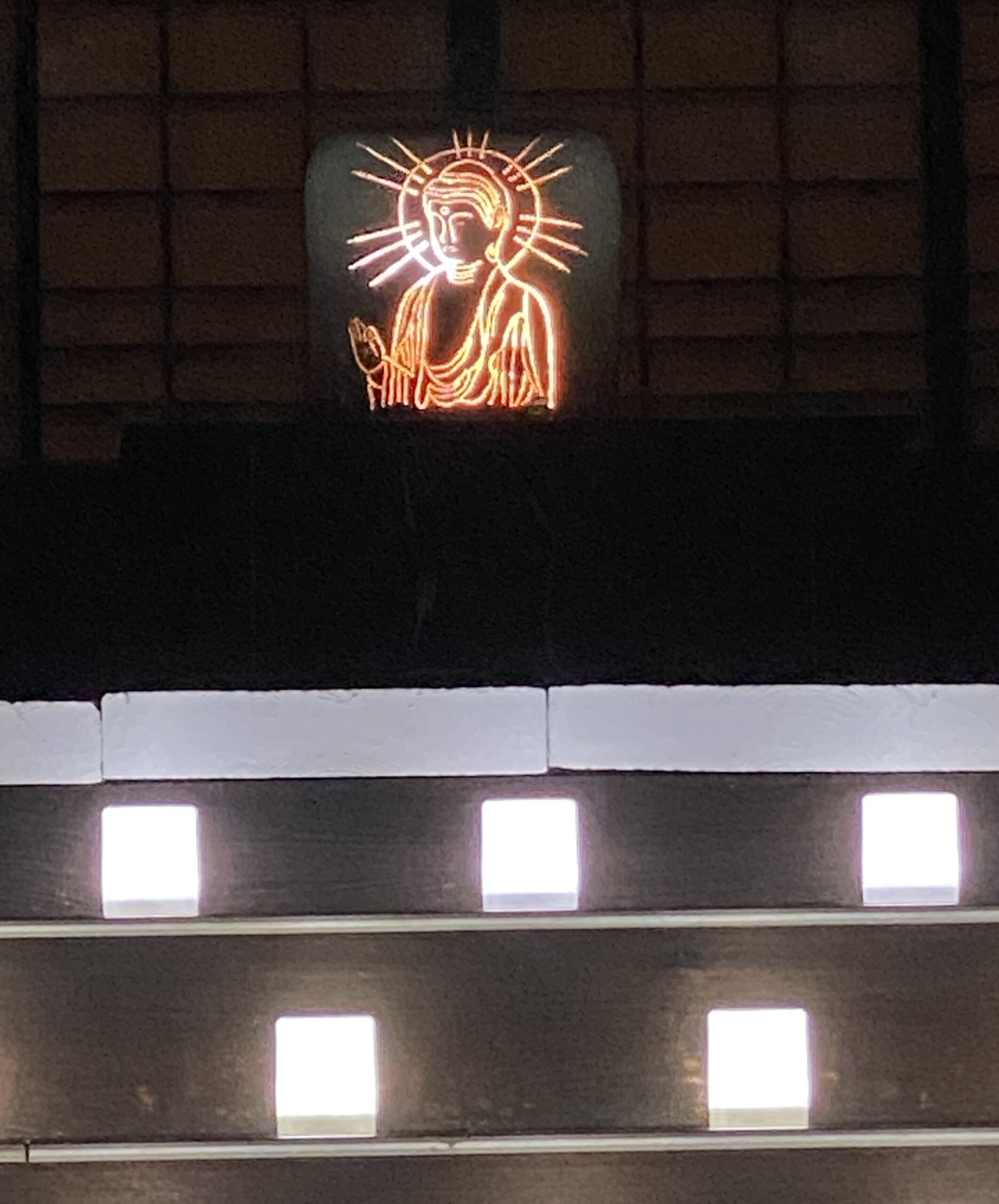法のたより〔274〕
盲亀浮木(もうきふぼく)
お釈迦様がお弟子たちに問いかけます。
「目の見えない亀(盲亀)が海の底に住んでいる。その亀が100年に一度、海の上に頭を出すことがある。そのときに海の浪間に木の切れ端が浮いている。その浮木には亀が頭を出すくらいの穴が開いている。広い広い海で目の見えない亀が探すことも出来ない状況で、浮木の穴から頭を出すということがあるだろうか?」
お弟子たちは一様に「そんなことは有り得ません。とっても無理なことです。」と、答えた。
お釈迦さまは、「絶対に有り得ないか?そう言い切ることが出来るか?」と、お弟子に聞きます。
お弟子は、
「絶対に有り得ないかと言われれば、何億年、何兆年、何億兆年の間には、ひょっと頭を出すことがあるかもしれませんが、無いといってもいいくらい、難しいことです。」と、答えました。
お釈迦さまは、
「弟子たちよ。私たちが人間に生まれることは、この盲亀が、浮木の穴に頭を入れることほど、希の中にも希なことなのだよ。それほど難しい出来事として、たいへん有ることの難しいことなのだよ。」と、諭されたといわれています。
(これが「ありがとう(有り難い)」の言葉の始まりといわれています)
地球上の生き物、人間だけでなくて犬、猫、鳥、ミミズ、昆虫、バクテリア、などなど150万種類ともいわれる多くの生き物が存在するそうです。
その中で人間に生まれるということはたいへん難しいことです。
また、その中で、親子となり、夫婦となり、兄弟姉妹、と縁を結んでいくことは希なことです。
私が生まれ出てくるためには両親、祖父母、曾祖父母と先祖を遡っていくと、10代先祖を遡ると1024人、20代遡ると104万8576人、27代遡ると日本人の人口をはるかに超える1億3421万7728人にもなるそうです。この中の一人として欠けても私は今ここに居る事が出来なかったのです。こうなると他人と思っている人々も、どこかで何かしらのご縁で結ばれているということになります。そんないのちのつながりの中で私の命が今ここに有らしめられているのです。不思議としか言いようがありません。このことを「盲亀浮木」の譬は教えているのでしょう。当たり前でない有難い人間としての命。
そのことを親鸞聖人が七高僧と尊ばれたお一人の源信和尚は横川法語(よかわほうご)として、次のように示されています。
「まず三(さん)悪道(まくどう)を離れて人間に生るること、大なるよろこびなり。
身は賤(いや)しくとも畜生(ちくしょう)に劣らんや、
家は貧しくとも餓鬼(がき)に勝るべし、
心に思うことかなわずとも地獄(じごく)の苦に比ぶべからず。(横川法語)」
三悪道(地獄・餓鬼・畜生)に生まれて当然だった私が、今、前生の縁が整って人間に生まれさせていただくことが出来たよろこびは量り知れないものである。ということを源信和尚はお伝えくださっています。
『人生のみちしるべ』のなかで稲垣瑞剱先生は
「人間は自分が人間でありながら「人間」とはどんなものかということを知らない。人間とはこんなものだと知ることは大切なことであるが、知ったと思うているのは、まだ本当に知っていない。自分の知識も、学問も、人間たる意識も忘れて、いつしか大自然の中にとけ込み、自己を忘れて、真の自己に帰り、仏の大慈悲が、自分を通して活動するようになったら、それが真の人間というものであろう。(中略)どうしても自分は「わけへだて」を為し、「愛情」にほだされている人間だと自覚するならば「慚愧(ざんぎ)」するより外はない。「慚愧」することのみが普通人に許される唯だ一つの善根である。「慚愧」とは天にはじ、地にはじ、自己にはずることである。」と、
お釈迦様の教え「仏法」を聞いて、仏の大慈悲を心がけていき、「慚愧」と「感謝」の中に日々を過ごすことを勧められています。
報恩講に当たり、親鸞聖人のみ教えにふれる事が出来るのも「盲亀浮木」の譬が示すように希なことです。この好機を逃すことなく、しっかりとお聴聞させていただきましょう。